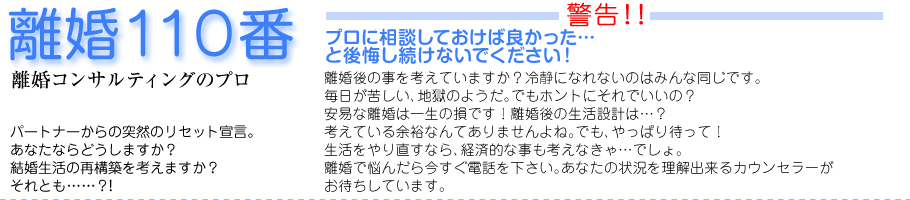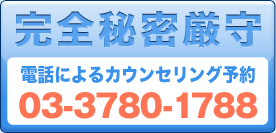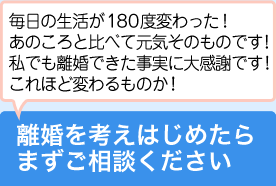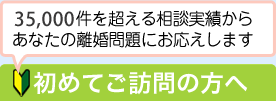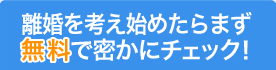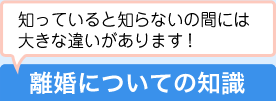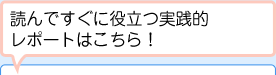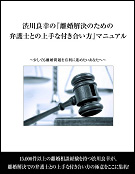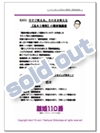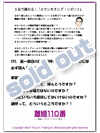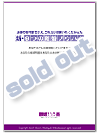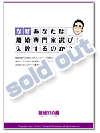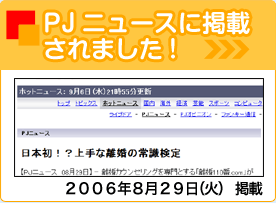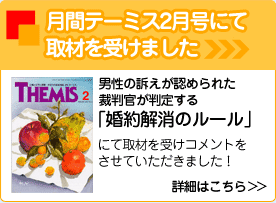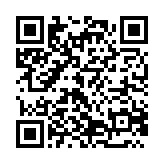離婚相談、カウンセリング専門サイト
「離婚110番」トップページ-離婚110番(電話 03-3780-1788)(メール info@rikon110.com )(携帯サイトはこちらです : http://www.rikon110com/mobile/ )
子供のいる離婚
親権者は誰にするのか?
身上監護権
子の身のまわりの世話や、しつけや教育をしたり法の定めている身分行為の代理人となる事です。
財産管理権
子が自分名義の財産を持っていて法律行為をする必要があった場合に、子に代わって財産の管理をする事です。
親権者の決定方法
離婚をする際にどちらが子供の親権者になるか協議で決定されれば問題はありませんが、お 互いが親権者になる事を望んでいるなど協議で決定しない場合は家 庭裁判所へ「親権者指定」の調停、審判の申立てをすることになります。
それでも決まらない場合は地方裁判所に離婚訴訟を提起する事になります。乳幼児~10歳くらいまでは母を親権者として適当であると判断する裁判例が約80%と多いといえます。詳しい基準は以下の通りになっています。
親の事情
父母の心身状況、子供に接することが出来る時間の程度、子育てをするのにふさわしい環境にいるか、経済状況 等
子供の事情
年齢、性別、父母どちらといたいと思うか、父母それぞれの結び付き、親の離婚後に変化する環境 等
家庭裁判所の「親権者指定」の手続きでは子供が15歳以上のときは「親権者指定」について必ず子供の意見が必要となります。
決定した親権者の変更
一回決定した親権者を変更するには家庭裁判所に「親権者変更」の調停、審判を申立てなければなりません。認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっています。
養育費用はどうするのか?
養育費は具体的な負担額支払方法が問題となりますが、夫婦それぞれの収入や財産、子供にこれまでかかった費用などを考えて決める事になります。
話がつかないときや仕送りを約束しておきながら約束を守らない時などは、家庭裁判所に養育費請求の申し立てが出来ます。家庭裁判所で相手方を呼び出して養育費の適当な額と支払いを決めてもらいます。
養育費負担義務
原則として親である限り、親と子が一緒に住むか住まないか、親権の有無、借金や負債の有無、などに関わらず未成年の子供に対して自分と同じ程度の生活が出来る金額の養育費を支払う義務の事を言います。
養育費の額
法律では一人あたりいくらと規定があるわけではありませんが、これは養育費を支払う側の収入によって左右されてきます。
平均で子供1人の場合月2~4万円が約半分を占めており、2人で4~6万円、3人で5~7万円が一番多くなっています。
支払期限と支払方法
通常は子供が成人するまでとなっていますが、中には高校を卒業するまでというケースや大学卒業するまでというケースもあります。
支払方法は子供名義の口座に毎月定めた期日に養育費を支払う方法が多いようです。
養育費の支払いが滞った場合
毎月確実に支払いをさせる事は意外と難しいようです。もしも養育費の支払いが滞った時のために公正証書で合意内容を決めておくのが良いでしょう。
(養育費でだけでなく財産分与、慰謝料の場合も同様)公正証書があれば支払わない相手に対して強制執行することが出来ます。
しかし強制執行の申立てには時間と費用がかかるために養育費のように一ヶ月に支払われる額が少ない場合にはあまり適していないのが現状です。
子供の苗字はどうするのか?
離婚後にどちらか一方が旧姓に戻っても子供はそのままの姓になります。
もし、親権者と子供の姓が別々になった、戸籍が別々になった子供を自分の戸籍に入籍させたいなどというような場合は家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。子供が15歳以上であれば子供自身で申立てを行えます。
面会交流権について
親権も監護権も取れなかったとしても子供に面会、電話、手紙、訪問等で接触する権利はあります。
法律では親が自分の子供と面会交流する権利を明確にはしていません。
しかし子供の側に立ってみれば離れて暮らす事となった親と会う権利は当然あると考えるべきで、「離れた親と会いたい」と願う子供の為の権利と言って良いでしょう。